「申し訳ありませんが、クラウドファンディングが成功しすぎました!」非営利団体にとってはあまり想定しない事態かもしれませんが、まさにそれを経験したのが、日本のスタートアップ企業Atmophです。Kickstarterでのキャンペーンが大きな反響を呼んだのです。クラウドファンディングは、日本と米国の非営利セクターにとって、従来型の助成金や既存の寄付者ネットワークに代わる重要な資金調達手段となっています。しかし、両国でのクラウドファンディングの構造、規制、そして社会的な受け止められ方には大きな違いがあります。本記事では、その違いと成功事例を分析しながら、非営利団体が自らの戦略を洗練させ、より大きなインパクトを生み出すためのヒントを探ります。
ターゲット型クラウドファンディングの台頭
日米の非営利団体から学ぶこと

日本のクラウドファンディング 成長中だが規制も多い分野
日本では、Readyfor、Campfire、AirFundingなどのプラットフォームが、非営利団体やソーシャルアントレプレナーに新たな資金調達の機会を提供しています。日本のクラウドファンディング文化は、共同体意識や社会的調和といった価値観を反映し、コミュニティベースの取り組みが主流といわれています。実際、支援者は、具体的で明確なローカルインパクトを目指すプロジェクトにより共感し、支援する傾向があります。
一方で、制度面ではアメリカに比べて制限が多く、寄付型やリターン型のクラウドファンディングには資金決済法が適用され、登録義務や情報開示義務が課されます。さらに、株式や持分を提供する投資型クラウドファンディングは金融商品取引法の対象となり、追加的なコンプライアンス対応が求められます。これらの規制は消費者保護を目的としていますが、非営利団体にとっては、活動の拡大を妨げる事務的負担となる場合もあるのです。

米国では、クラウドファンディングの規制環境が比較的柔軟で、非営利団体にとって実験的・革新的な試みに取り組みやすい土壌があります。株式型クラウドファンディングは2012年のJOBS法によって連邦レベルで規制されていますが、非営利団体が多く利用する寄付型クラウドファンディングは州レベルの規制と各プラットフォームのガイドラインに委ねられています。GoFundMe、GlobalGiving、Indiegogoといったプラットフォームでの活動が盛んです。
文化的にも、米国のクラウドファンディングは「大きな夢と感動的なストーリー」を重視する傾向があります。魅力的な登場人物、スケーラブルな成果、そしてソーシャルインパクトの可能性が語られ、まるで映画のような構成で支援を呼びかけます。SNS、Eメールキャンペーン、インフルエンサーとの連携といった高度なデジタルマーケティング戦略を活用し、支援者との関係構築にも力を入れています。短期的な資金調達だけでなく、長期的な支援者ネットワークの構築にも貢献しているのです。
共通する課題
一見対照的な両国のクラウドファンディングですが、非営利団体が直面する課題には共通点も多くあります。
- 規制の壁:日本では厳格な法令遵守が求められ、米国では税務上の透明性と詐欺防止への配慮が必要です。
- 支援者の維持:一度限りの支援に終わるケースが多く、継続的な支援を得るのが難しいという課題があります。
- 認知度の確保:オンライン上に数多くのキャンペーンが乱立する中、目立つ存在になるのは簡単ではありません。
- プロジェクト遂行のリスク:目標を達成できない場合、団体の信用や支援者の信頼を損なう可能性があります。
成功事例に学ぶ 創意工夫が生むインパクト
こうした課題を乗り越え、成果を上げている非営利団体も少なくありません。以下は、日米それぞれからの注目事例です。
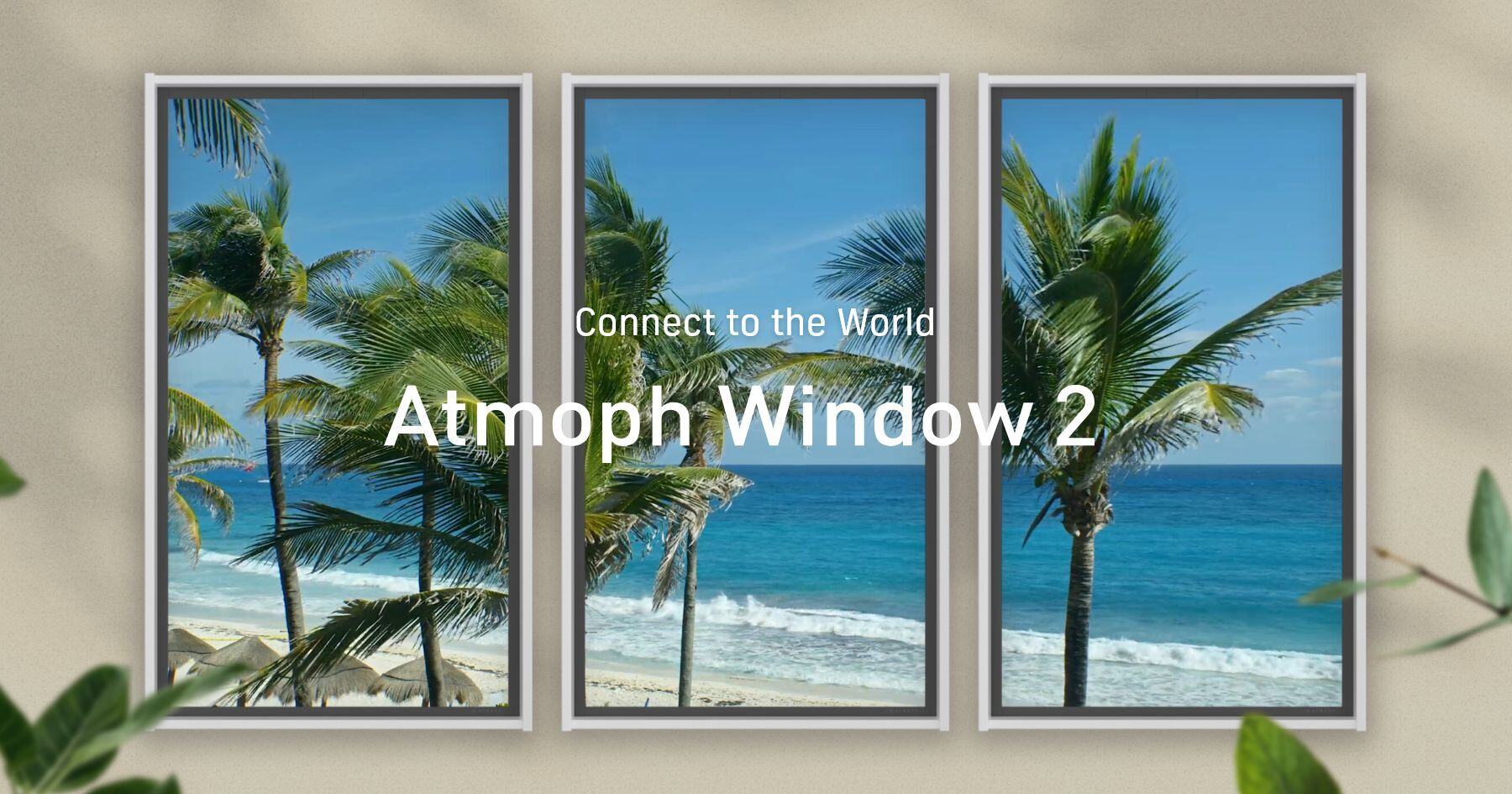
日本のスタートアップAtmophは、景色を映し出す「デジタル窓」Atmoph Window 2をKickstarterで発表し、約16万ドル(約2,000万円)を調達しました。しかし、予期せぬ製造コストや納期遅延が発生し、プロジェクトは危機的状況に陥りました。そこで彼らは、Makuakeでの第2のクラウドファンディング、政府系融資、ベンチャーキャピタルからの資金調達という複数の資金源を活用し、プロジェクトの継続を実現しました。
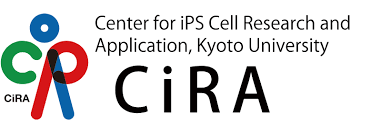
京都大学のiPS細胞研究所(CiRA)は、山中伸弥所長のリーダーシップのもと、最先端研究を支援するためにクラウドファンディングを実施しました。山中氏が京都マラソンにチャリティランナーとして参加したことが話題となり、JustGiving(現JapanGiving)を通じて約1,000万円(約6万6,900ドル)を集めました。この取り組みは、CiRAの資金確保に貢献しただけでなく、日本における科学分野のクラウドファンディングの認知向上にもつながりました。

小児医療を支援するRiley Children’s Foundationは、支援者の層を拡大するという課題に取り組みました。Giving Tuesdayに合わせて、動画と視覚的インパクトのあるメッセージでキャンペーンを展開し、寄付金の使い道を明確に伝えることで支援者の共感を得ました。SNS活用とパーソナライズされたアプローチにより、寄付額が前年比19%増加、年末の寄付総額も22%アップという成果をあげました。デジタル戦略ディレクターはこう語っています。「私たちは単に物語を語ったのではありません。支援者をその物語のヒーローにしたのです」

児童性的虐待の根絶を目指す非営利団体Sapreaは、センシティブなテーマを扱う上で、被害者の尊厳を尊重しつつ、問題の緊急性を伝えるストーリーテリングを展開しました。この慎重で戦略的なメッセージングが奏功し、Giving Tuesdayキャンペーンを通じて、1年以内に追加で4万ドル(約590万円)を集めることに成功しました。
非営利団体が学べること
上記の事例から、日米の非営利団体が活用できる重要なポイントが見えてきます。
クラウドファンディングの進化に伴い、日米の非営利団体はお互いから学び合うことができます。たとえば、日本の団体にとっては、米国のキャンペーンで用いられるストーリーテリングの手法が参考になるかもしれません。一方、米国の非営利団体は、日本のようなコミュニティ重視の関わり方を通じて、支援者との関係をより深められる可能性があります。それぞれの文化に根ざした優れた実践例を取り入れることで、より強固で持続可能なクラウドファンディング戦略を構築し、長期的なソーシャルインパクトにつなげていくことができるでしょう。
越境型クラウドファンディングに挑戦しませんか?
物語性を強化したい日本の非営利団体も、コミュニティとのつながりを深めたい米国の団体も、米日財団(USJF)は皆さまの挑戦を全力で応援します。私たちは、市民社会の強化と日米の協働の促進を使命としており、クラウドファンディングを通じた革新的な取り組みの実現を支援しています。
日米間の越境型クラウドファンディングを成功させるために、私たちと一緒に次のステップを踏み出しませんか?詳細は米日財団のウェブサイトをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。一つひとつのキャンペーンが、二国間の橋を築く力になります。

